ブログ BLOG


- 新着記事
- 【八潮市の塾選び】集団?個別?失敗しないための比較と選び方を塾長が解説
- 【塾選び】集団か個別か?八潮で悩むママへ。塾長が実体験から語る「本当に伸びる塾」の条件
- 「どこが良いのか分からない…」八潮市の塾選びで失敗しないための比較&チェック
- 【八潮市ー受験生】【公立高校入試まであと2週間】今からでも点数を伸ばす「最後の追い込み法」
- 八潮市で幼児から英語を始めるなら?「勉強」にならない遊びの工夫
- 【八潮市】個別指導塾に通っても成績が上がらない子の5つの共通点
- 【潮止中 塾】遠くても選ばれる理由|バスで通う生徒もいる「まなびの樹」
- 【八條中 近く 塾】通いやすさ+成績アップなら「まなびの樹」
- 【八幡中 近く 塾】部活と両立して成績が伸びるのは「まなびの樹」
- 【大原中 近くの塾】部活と両立して成績が伸びるのは「まなびの樹」
- カテゴリー
- まなびの樹の教え方(228)
- イベント・お知らせ(12)
- 小学生向け勉強方法(114)
- 中学生向け勉強方法(205)
- 高校生向け勉強方法(74)
- 英語学習方法(47)
- 学童保育について(67)
- 高校受験情報(9)
- 生徒・保護者の声(4)
- 成績・合格実績(20)
- 大学受験情報(5)
- アーカイブ
- 2026年02月 (15)
- 2026年01月 (60)
- 2025年12月 (9)
- 2025年11月 (5)
- 2025年10月 (15)
- 2025年09月 (3)
- 2025年08月 (1)
- 2025年07月 (1)
- 2025年06月 (4)
- 2025年05月 (3)
- 2025年02月 (7)
- 2025年01月 (1)
- 2024年12月 (5)
- 2024年11月 (5)
- 2024年07月 (3)
- 2024年06月 (5)
- 2024年05月 (13)
- 2024年04月 (3)
- 2024年03月 (8)
- 2024年02月 (9)
- 2024年01月 (11)
- 2023年12月 (8)
- 2023年11月 (5)
- 2023年10月 (13)
- 2023年09月 (13)
- 2023年07月 (14)
- 2023年06月 (23)
- 2023年05月 (20)
- 2023年04月 (16)
- 2023年03月 (4)
- 2023年02月 (3)
- 2023年01月 (2)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (1)
- 2022年09月 (4)
- 2022年07月 (3)
- 2022年06月 (1)
- 2022年05月 (4)
- 2022年03月 (8)
- 2022年02月 (6)
- 2022年01月 (5)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (13)
- 2021年10月 (16)
- 2021年09月 (6)
- 2021年08月 (6)
- 2021年07月 (29)
- 2021年06月 (4)
2025.05.08
算数・数学で大切なこと
最近よく思います。算数・数学の基礎はマニュアル作業だと。
基礎問題は決められた公式を決められた手順で処理をすれば正解が出ます。
標準問題、基礎問題、と言われる問題は、基礎問題の組み合わせができるかどうかだけです。
東大の問題は基礎と基礎の組み合わせで解ける、というCMをみましたが本当にそうだと思います。
どんなに凄い問題でも時間内に思いつくかどうかはありますが基礎が身についていれば解けます。
◯算数・数学で大切なこと
入塾して時間が間もない生徒たちが先生に注意されることがあります。
それは、「途中式を丁寧に書きなさい」ということです。
はっきり言います。人間の頭はそこまで賢くありません。
その場で覚えてられるタスクは7個程度と言われています。
私なんかは3つぐらいしか覚えられません。
サラリーマン時代は20から30案件程度を回していたので当然覚えられません。
ひたすらメモをして、記録して、記録したものを見ながら案件を進めていました。
何が言いたいか、というと、算数・数学ができない、点が伸びない生徒ほど「途中式」を丁寧に書きません。
1行に1計算しかしちゃだめだよ、と何度言っても、めんどくさがって数個の計算処理を一気にやろうとして、間違えます。
正直、小学生のときに計算が得意!と思っている生徒ほどこの傾向が強いです。
いやいや、中学生になると通用しませんよ。
中学生になると小学生とは比べものにならないぐらい計算処理が多くなります。
小学校のテストレベルであれば暗算で解けたかもしれませんが中学では無理です。
1学期の正負の数で2つぐらいの数字であれば大丈夫ですが、4つぐらい数字が出てくると計算ミスのオンパレードです。
そう先ほどの話です。
人間のあたまはあまり良くありません。
数が多くなると計算をしている最中に計算をして出した数字を覚えてられないんです。
加えて符号の処理が出てくると尚更です。分数が出てくるともうアウトです。
覚えきれないので、頭が処理できずにミスをします。
では、どうするか。
そう、メモをする=途中式を書く、です。
もう間違い無いです。高校生でも同じです。
数学が苦手だ、という生徒ほど途中式が雑です。
数学が得意だ、という生徒ほどどう計算したのかわかるような途中式を書きます。
生徒の学力を見る際にテストの結果だけでなく、よくノートを見ます。
ノートが綺麗な生徒は量をこなせば伸びるな、と判断しますが、ノートが汚い生徒は伸び悩むな、と本当に思います。
ノートが綺麗=思考が整理されている。
ノートが汚い=思考が整理されていない。
そう考えられるからです。
もちろん例外の生徒もいますが、結構当たります。
子供のノートを見て、見やすいなぁと感じたら良い傾向です。
汚い、読みづらい、と感じたら少し注意です。
算数・数学の基礎の一つ一つについて、やりかた自体はそこまで量が多くなく、難しくもありません。
英単語や漢字のように大量に覚える必要もありません。
しかし、覚えたからと言ってその正しい手順通りに処理を行わないと答えが出てこない科目でもあります。
逆に手順通りにやればしっかり点が取れる科目です。
手順通りにやる。そのために式を丁寧に書く、忘れないために書く、この作業をするだけで点が取れます。
◯まとめ
正直数学が苦手だ、という理由に途中式を書こうとしない生徒を見ると将来が不安です。
マニュアルのない会社はないと思いますが、そのマニュアルを見もせず、マニュアル通りに作業せず、失敗する姿を想像してしまいます。
本当にそういう社会人もいました。
完全に自業自得だと思いますが社会に出るとそんなに優しくないので皆から白い目で見られていました。
そうならないといいなぁ、と思います。
応用問題ができるかどうかは好き嫌いの領域もありますし、思いつけるかの思考力も関係すると思いますが、少なくとも計算問題ができない、と言っている生徒は本当にそう思います。
途中式を書く=メモを取る、という習慣に直結します。
メモを取って、手順通りにやればできます。
急がば回れ、正解したいならば途中式をしっかり書きましょう。
大量に練習しているとそのうち自分なりの計算手法を開発でき、計算も早く処理できるようになります。
そこまでは丁寧に書きましょう。
なんでも守破離です。まずはルールを正しく覚えて、ルールを手順通りにやりましょう。
早く処理する、はその先です。
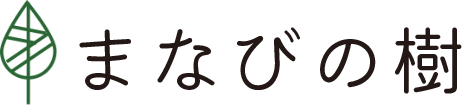
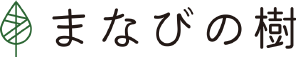

 お気軽にご相談ください
お気軽にご相談ください
