ブログ BLOG


- 新着記事
- 4月の小学校入学まであと3ヶ月!学童選びで差がつく子どもの成長
- 中学入学まであと3ヶ月!スタートダッシュ準備講座
- 高校生で塾に通う意味はあるのか? | 八潮市の学習塾
- 小学生こそ復習をしよう | 八潮市の学習塾
- 学童で宿題をやらせるだけでは足りない理由 | 八潮市の学童
- 少人数制の学童だから起きること | 八潮市の民間学童
- すべての事業において大切にしていること
- 外遊びは身体と心を育む万能薬 | 八潮市の民間学童
- あなたは何故英語を勉強するのですか? | 八潮市の英語教室
- 英語は精読が大切 | 八潮市の学習塾
- カテゴリー
- まなびの樹の教え方(228)
- イベント・お知らせ(12)
- 小学生向け勉強方法(110)
- 中学生向け勉強方法(181)
- 高校生向け勉強方法(70)
- 英語学習方法(40)
- 学童保育について(27)
- 高校受験情報(9)
- 生徒・保護者の声(4)
- 成績・合格実績(20)
- 大学受験情報(3)
- アーカイブ
- 2026年01月 (2)
- 2025年12月 (9)
- 2025年11月 (5)
- 2025年10月 (15)
- 2025年09月 (3)
- 2025年08月 (1)
- 2025年07月 (1)
- 2025年06月 (4)
- 2025年05月 (3)
- 2025年02月 (7)
- 2025年01月 (1)
- 2024年12月 (5)
- 2024年11月 (5)
- 2024年07月 (3)
- 2024年06月 (5)
- 2024年05月 (13)
- 2024年04月 (3)
- 2024年03月 (8)
- 2024年02月 (9)
- 2024年01月 (11)
- 2023年12月 (8)
- 2023年11月 (5)
- 2023年10月 (13)
- 2023年09月 (13)
- 2023年07月 (14)
- 2023年06月 (23)
- 2023年05月 (20)
- 2023年04月 (16)
- 2023年03月 (4)
- 2023年02月 (3)
- 2023年01月 (2)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (1)
- 2022年09月 (4)
- 2022年07月 (3)
- 2022年06月 (1)
- 2022年05月 (4)
- 2022年03月 (8)
- 2022年02月 (6)
- 2022年01月 (5)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (13)
- 2021年10月 (16)
- 2021年09月 (6)
- 2021年08月 (6)
- 2021年07月 (29)
- 2021年06月 (4)
2025.02.18
勉強=覚える?勉強=理解する
勉強は覚えることが多くて大変だ!という生徒がいます。
確かに覚えることは多いのですが、どうやって覚えるか、が問題です。
覚え方を間違えると応用ができなくて点数が伸び悩みます。
◯勉強=覚える?勉強=理解する
勉強で大切なのは覚える、ではなく理解する、です。
もちろん覚える必要があることもあります。
そうそう、漢字や英単語、公式を覚えるの大変だよね、、という発想をしたあなたは間違ってます。
その漢字や英単語、公式をまる覚えしようとしてませんか?
もちろん覚えることも多いのですが、覚える際に意味まで理解しておくとより簡単に覚えられたり、応用が効きます。
例えば漢字の作りや英単語の形です。
漢字であればさんずいは水を表す漢字とか、土辺は土を意味する漢字とか、そういうものです。
inter- ならば内部を意味する、exter-なら外部を意味する、など言葉が持つ意味を理解すると、より早く覚えることができます。
数学の公式も一緒です。
ただ文字として覚えて、当てはめるよりも、なぜその公式があるのか。
公式の意味は何なのか、を理解することが応用が聞くようになります。
三角柱ならば、三角形という平面が1面あり、それが高さ分だけあって三角柱になるので、公式は三角形の面積✖️高さなんだな、とか。
この意味を考えることでより深い知識となり、逆に覚えやすくなったりもします。
生徒たちの中には覚えようと思うと、フォトリーディングのごとくその形を覚えるだけの生徒がちらほらいます。
数が少ないうちはそれでも何とかなりますが、量が多くなってくるとそれこそ覚えきれません。
理科、社会も実は同様です。
深い知識、応用が解けるようになりないならば、表面上の情報だけでなく本質的な理解をする、ということがとても大切です。
◯まとめ
社会に出ても同じだと思います。目の前で起こった結果・事実をどう考えるか。
考えられる人は課題を解決できますが、結果・事実だけみて対処のみ考えている人は対処法がないと思考停止してしまいます。
なぜその結果・事実が生まれたのか。これを考える癖というのは学校の勉強習慣から身につけられます。
目の前で覚えなさい!とただ言われたことに対して、しっかりとなぜ?という発想を持つことが結果的に早く覚えられ、応用もできるようになっていきます。
覚えることが得意な生徒ほど考える癖がないので注意して欲しいのですが、覚えるだけならAIに勝つことはできません。
なぜ?という思考をする癖をつけていきましょう。
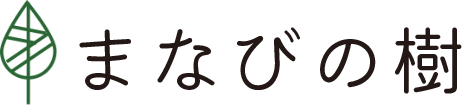
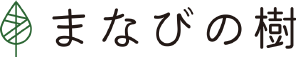

 お気軽にご相談ください
お気軽にご相談ください
