ブログ BLOG


- 新着記事
- 【八潮市】数学が苦手でも大丈夫?八潮で選ばれる塾「まなびの樹」の数学指導とは
- 【八潮市】部活と塾は両立できる?まなびの樹が実践する“続く学習スタイル”
- 【八潮市】小3で学童を辞めた後の「YouTube・ゲーム三昧」を防ぐ!放課後をダラダラさせない新習慣
- 【共働き家庭の悩み】小3の学習難化にどう向き合う?
- 「学童+塾」の送迎に限界を感じたら。八潮で完結する“一石二鳥”の放課後の過ごし方
- 小3から急増する「算数ギライ」。学童任せにできない単元ワースト3と解決策
- 「宿題やったよ」を信じていい?八潮の放課後を“学びの黄金時間”に変える方法
- 学童は「学習塾」ではない。小3の学習内容を家庭やプロがフォローすべき3つの理由
- 【八潮市の塾選び】集団?個別?失敗しないための比較と選び方を塾長が解説
- 【塾選び】集団か個別か?八潮で悩むママへ。塾長が実体験から語る「本当に伸びる塾」の条件
- カテゴリー
- まなびの樹の教え方(228)
- イベント・お知らせ(12)
- 小学生向け勉強方法(114)
- 中学生向け勉強方法(207)
- 高校生向け勉強方法(74)
- 英語学習方法(47)
- 学童保育について(73)
- 高校受験情報(9)
- 生徒・保護者の声(4)
- 成績・合格実績(20)
- 大学受験情報(5)
- アーカイブ
- 2026年02月 (23)
- 2026年01月 (60)
- 2025年12月 (9)
- 2025年11月 (5)
- 2025年10月 (15)
- 2025年09月 (3)
- 2025年08月 (1)
- 2025年07月 (1)
- 2025年06月 (4)
- 2025年05月 (3)
- 2025年02月 (7)
- 2025年01月 (1)
- 2024年12月 (5)
- 2024年11月 (5)
- 2024年07月 (3)
- 2024年06月 (5)
- 2024年05月 (13)
- 2024年04月 (3)
- 2024年03月 (8)
- 2024年02月 (9)
- 2024年01月 (11)
- 2023年12月 (8)
- 2023年11月 (5)
- 2023年10月 (13)
- 2023年09月 (13)
- 2023年07月 (14)
- 2023年06月 (23)
- 2023年05月 (20)
- 2023年04月 (16)
- 2023年03月 (4)
- 2023年02月 (3)
- 2023年01月 (2)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (1)
- 2022年09月 (4)
- 2022年07月 (3)
- 2022年06月 (1)
- 2022年05月 (4)
- 2022年03月 (8)
- 2022年02月 (6)
- 2022年01月 (5)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (13)
- 2021年10月 (16)
- 2021年09月 (6)
- 2021年08月 (6)
- 2021年07月 (29)
- 2021年06月 (4)
2021.07.14
理科の学び方
理科というと私のイメージは「実験」という記憶です。学校の実験室や校庭、庭で色々なことをする楽しい授業というイメージです。観察カードを書いたり、レポートを作ったり、そんなイメージの科目ではないでしょうか?
理科はSTEM教育のScience です。今IT化が進む中でより注目されている科目になり、重要度も高くなっています。その理由はなんでしょうか?
理科の勉強というとどうしても実験的なものを思い出してしまいますが、大切なのは「何をやるか」、ではなくて、「なぜそうなるのか?」という考える力です。
理科が得意な子供は、なぜその事象が起きるのか、という興味を追える子供です。自分の興味を興味に沿って、まなぶことができれば、最高だな、と思う科目です。恐らく理科が得意なお子さんは探求学習も得意なはずです。このなぜ?という思考癖がついているからです。
疑問に思わず、作業として実験やその他の活動を捉えると、楽しい!と感じて終わってしまったり、作業がつまらない、という感想だけで終わってしまうかもしれません。
◯理科の題材
理科の教科書を見直しても、勉強の際に題材になるのは日常生活で触れるものばかりです。
火、水、土、太陽、月、植物、動物、化学反応、etc
確かに暗記する内容が多いのも事実ですが、理科において大切なのは、なぜそうなるのか、ということを本当に理解することです。
恐らく、この質問をすると、答えられない先生がいる可能性がある、(私も答えられない可能性あり)非常に高度な科目だと個人的には思っています。
この、なぜ?という思考の癖をつけることが、理科が得意になる秘訣です。
ただ単に影が伸びるのは、太陽との角度が変わるから、ではなく、ではなぜ角度が変わるのか。地球の自転という仕組みと、太陽系の仕組みがあるから、と少し「なぜ?」という疑問を持つだけで知識の深掘りが必要になり、また理解すると「なぜ」その事象が起きるのか、が論理的にわかってきます。
この思考の癖が学べるのが「理科」という科目だと理解していて、この力が将来必ず必要になるため、あえてSTEM教育、と名がつくほど「理科」の力を強化する流れになっています。
◯社会で必要な科学力
理科、という科目だけで考えると確かに世の中の自然現象の学びも深まり、教養として非常に知識深い大人になれると思いますが、社会で働いている方々であれば、お気づきだと思います。
何か問題が発生した際に、対処法をマニュアルのみで対応する人と、問題の原因に対して「なぜ起きたのか?」を考えた上で対処行動ができる人、どちらが市場価値が高いでしょうか。
今後はIT化、AI化が進んで、マニュアル作業に関しては次々に機械にとって変わられる時代になります。お約束します。では、人間がやることはマニュアル外のことになりますが、そうなった時に、マニュアルに載っていない事象に対して、「なぜ?どうして?では、どうしよう」という思考の癖と、調べる行動力、答えを導く力、こういう能力が大切になります。
他の教科においては、そこまで「なぜ?」という思考が必要になる科目がありませんが、本当に理科という教科をマスターしようと思うとこの「なぜ?」という思考癖が必須になります。
どうしても理科という科目だけ聞くと将来、科学者や発明家になる人が勉強するイメージが個人的に強いのですが、理科を楽しむと将来的にはとても有望な思考力が養われます。
◯どう鍛えるか
子供が小さい頃に聞かれたことがあるかもしれませんが、「なんで空は青いの?」こういう問いを大切にしていくこと、またこういう問いを子供にしてあげることが大切です。
ただ単に教科書を読んで覚えるだけですと、単なる暗記の科目になってしまい、点数は取れるかもしれませんが、本質的な「まなび」にはなりません。
日常の生活の中で、普通にできていることに対して、「なんで?」という疑問を投げかけてあげると良いと思います。
実際に子供が質問してきたら、一緒になって調べてあげると良いと思います。
恐らく大人でもわからないような疑問を投げかけて来る場合もあると思いますが、その場合は一緒に楽しみながら調べていくと良いと思います。
◯まとめ
理科の科目では国語力、算数力も微妙に求められますが、なんといっても「なぜ?」という探究心が大切な科目です。
日ごろから「なぜ?」という力を養っていけば、理科の科目については得意な科目になってくると思います。教科書が説明していることに対して、理屈を付けて解説ができるようになるからです。
NHKのチコちゃんの番組ではありませんが、ぼーっとしていると答えられない質問ばかりが飛んでくる可能性がある、親としては一番厄介な科目ですが、一番面白い科目かもしれません。
まなびの樹では、もちろん「すらら」という教材を利用しますが、なるべく、「なぜ?」という質問を投げかけ、「まなびの樹タイム」で、なるべく体験してもらえるようなやり方を模索したいと思います。
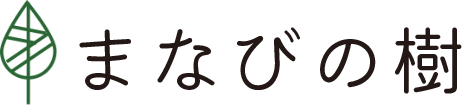
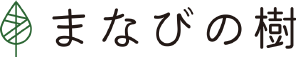

 お気軽にご相談ください
お気軽にご相談ください
