ブログ BLOG


- 新着記事
- 【潮止中 塾】遠くても選ばれる理由|バスで通う生徒もいる「まなびの樹」
- 【八條中 近く 塾】通いやすさ+成績アップなら「まなびの樹」
- 【八幡中 近く 塾】部活と両立して成績が伸びるのは「まなびの樹」
- 【大原中 近くの塾】部活と両立して成績が伸びるのは「まなびの樹」
- 【八潮中から近い塾を探している方へ】部活と勉強を両立できる学習環境の選び方
- 【八潮市の保護者・高校生へ】高校生にとって「塾の役割」とは?通う意味を改めて考える
- 【八潮市の新中1必見】小学校とは別世界?中学最初のテストで「つまずかない」ための春休みの過ごし方
- 【大曾根小】学童に落ちた…どうする?八潮市で後悔しないための現実的な対処法
- 【大瀬小】学童に落ちた…どうする?八潮市の保護者が知っておくべき3つの選択肢
- 【八潮市|新中1】中学英語は最初で決まる。「英語が得意な子」と「苦手な子」の差は春休みの〇〇だった
- カテゴリー
- まなびの樹の教え方(228)
- イベント・お知らせ(12)
- 小学生向け勉強方法(113)
- 中学生向け勉強方法(200)
- 高校生向け勉強方法(71)
- 英語学習方法(46)
- 学童保育について(67)
- 高校受験情報(9)
- 生徒・保護者の声(4)
- 成績・合格実績(20)
- 大学受験情報(5)
- アーカイブ
- 2026年02月 (9)
- 2026年01月 (60)
- 2025年12月 (9)
- 2025年11月 (5)
- 2025年10月 (15)
- 2025年09月 (3)
- 2025年08月 (1)
- 2025年07月 (1)
- 2025年06月 (4)
- 2025年05月 (3)
- 2025年02月 (7)
- 2025年01月 (1)
- 2024年12月 (5)
- 2024年11月 (5)
- 2024年07月 (3)
- 2024年06月 (5)
- 2024年05月 (13)
- 2024年04月 (3)
- 2024年03月 (8)
- 2024年02月 (9)
- 2024年01月 (11)
- 2023年12月 (8)
- 2023年11月 (5)
- 2023年10月 (13)
- 2023年09月 (13)
- 2023年07月 (14)
- 2023年06月 (23)
- 2023年05月 (20)
- 2023年04月 (16)
- 2023年03月 (4)
- 2023年02月 (3)
- 2023年01月 (2)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (1)
- 2022年09月 (4)
- 2022年07月 (3)
- 2022年06月 (1)
- 2022年05月 (4)
- 2022年03月 (8)
- 2022年02月 (6)
- 2022年01月 (5)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (13)
- 2021年10月 (16)
- 2021年09月 (6)
- 2021年08月 (6)
- 2021年07月 (29)
- 2021年06月 (4)
2023.04.18
定期テスト2週間前の勉強法
学校の勉強も少しずつ始まりましたね。
中学1年生は初めての定期テストでどういうものなかどきどきだと思いますし、新年度の生徒たちは今年こそは!という生徒もいると思います。
どこの塾もそうだと思いますが、まなびの樹では数学に関しては当該学期に勉強する内容が理解できるだけの復習が完了した生徒から予習学習を始めています。
ざっくりと学習カリキュラムは以下のように組まれています。
1学期は計算問題中心
2学期は関数+図形
3学期は図形+確率
前年に躓いていたら確実に今年度も躓くのでまずはしっかりと復習が必要です。
本来はその復習を長期休みの間にやっておくのがいいんですよね。
そこで、定期テストに向けて今一度口をすっぱくいっていることをまとめてみます。
◯定期テスト2週間前からやること
定期テスト前までにやることは基本的に全教科ワークの3周学習です。
3周学習とはワークを3回繰り返す、というものです。
前提は授業を聞いている、教科書を読んでいる、もしくは塾で勉強をしている、です。
そもそものインプットがなければアウトプットはできませんからね。
1周目はとにかくやってみて、その時点で「できる問題、できない問題を洗い出し」ます。
そして、できない問題は解説をみたり、先生に聞いて理解してもらい、解き直しをします。
解き直しをしなければ1周学習をやったとみなしません。
なぜなら、自分で問題を解けないのであれば意味がないからです。
しっかりとこのタイミングでできるようになりましょう。
答えを写して終わっている生徒は言わずもがな、実際に正しく1周学習ができていない生徒は平均点に届きません。。。
2周目は全部やり直す、という方法もありですが、時間がなければ1周目で間違った問題のみもう一度やることで良しとしてます。
1回目でできた問題は基本できると思います。
ただし、記憶系の科目や問題は別ですよ。
そして、テスト2、3日前から3周目の学習です。
記憶系は最終確認、計算系は不安に思ったところをもう一度解いてもらいます。
100点が取れる自信がつくまでやってもらうのがゴールです。
◯だめな例
今まで点が取れていない子達のだめな点をあげてみます。
・教科書を読んでいない
知識が足りていない生徒に多いのはそもそも教科書を読んでいない、という生徒です。授業中何をやっているんだ?というレベルですが、本当に読んでいません。インプットがなければ当然アウトプットができません。読んでいない生徒はワークをやる前にまずは教科書を読むことからです。
・塾の宿題をやっていないので知識の定着ができていない
まなびの樹でもそこそこの演習はやってもらいます。その上で足りない演習を宿題でやってきてもらいます。その宿題をやらない場合、当然演習量が少ないので、身につかないか、進度が遅くなります。そうすると試験範囲の学習がギリギリになってしまったり、同じような問題が取れなかったりします。
・定期テスト2週間前からワークをやる
ワークの提出があるので定期テスト対策の「勉強」というよりワーク提出のための「作業」になります。作業なので、頭に入ってこないので何も身につきません。最悪答えを写して終わりなので、点が取れるはずもありません。。
・解き直しをしない
時間がない場合に前項と同様に写して終わった場合、できるようになっていないので、試験でできるはずもありません。どちらかというと、このとき直しが一番大切です。とき直しができていなければ前回の点数を超えるはずはありません。
どうですか?あなたは、あなたのお子さんはどういう状態ですか?
◯口をすっぱくいっていること
なので、日々の通塾日に言い続けているのは、上記の状況を避けるため+高得点を取るため以下になります。
・教科書やワークを持ち帰り、日々の復習をすること
脳科学的にも1日1日の復習をし、1周間後にもう一度復習をすることが一番記憶の定着がはかれる方法とわかってます。
毎日重いですが教科書とワークを持ち帰り、その日にあった授業の復習+進んだ分だけワークを進めなさい、と言っています。おそらく30分もかからない勉強です。
わからない問題があったら学校の先生に聞くなり、塾で聞くなりして理解しておくことです。
これだけで定期テスト前に提出するのに慌てることだけでなく、記憶の定着や理解もできるので一石3鳥です。
やらない理由がわかりません。
・わからないことはわからない、と言いなさい
勉強は理解することがとても大切です。
わからないこと、理解できないこと、をわからない、と人にいうことで早く教えてもらうことができます。
わからない、と言える大人になるためにも、今のうちから恥ずかしがらずにわからない、と言えるようになろうと言ってます。
わかったつもり、が一番最悪です。
定期テストまでの学習でわからないことがなければ十分に高得点が狙えると思います。
・宿題はやったのか?
宿題を出すには目的があります。
学習習慣の定着、理解の定着、実力の確認、偏差値を高めるため学校ではやらないような問題を自力で解いてもらうため。
その子の実力に合わせて出しているので、その宿題をやってこない、ということは自分の成長を放棄しているようなものです。
やってこない場合、自分の目標を見失っているようなものなので、改めて何の目的で塾に来ているか考えてもらいます。
宿題は毎回生徒と合意の上出しています。先生と約束した形です。
毎回、できないような量を出しているつもりはありませんが、生徒も忙しいタイミングがあるとも思っているので、授業の最後に今日の宿題は量が多いかな?と生徒が思った場合は交渉してもらいます。
◯まとめ
勉強の量でだいたい今回の定期テストだとこれぐらいの点になるだろうな、と予想がつくようになっています。
ざっくりですが、以下のようなイメージです。
答えを写しただけの生徒:平均点以下
1周学習(とき直しをしている):平均点前後
2周学習:80点前後
3周学習:90点前後
結論として何が言いたいかというと、「日々勉強を頑張ろう」ということです。
しっかりと日々の復習をし、ワークを進めている生徒が結局は勝ちます。
毎日30分の積み重ねで大きな結果が生まれます。
テスト前だけ頑張ればいいや、で高得点が取れるのはよっぽど記憶力が良いか、
実は授業中にとてもよく先生の話を聞いて理解して、練習問題も授業中に解いてしまっている生徒のみです。
普通の子はしっかりと復習をがんばりましょう。
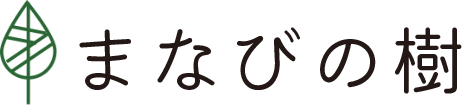
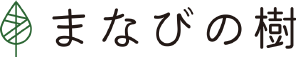

 お気軽にご相談ください
お気軽にご相談ください
